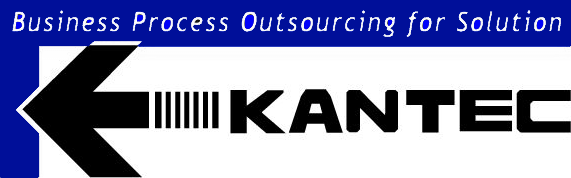こんにちは。BPOサービスを提供するカンテックのライターチームです。eKYCとは、オンライン上で本人確認が完結する仕組みです。この記事では、従来の本人確認方法であるKYCとの違い、eKYCの導入が増加している理由や導入のメリット、デメリットを解説します。個人情報を取り扱う業界のBPO担当者は、ぜひご参考ください。
eKYCとは
eKYCとKYCとの違い、2018年の犯収法改正について解説します。
KYCとの違い
KYCが郵送や対面で行う本人確認手続き(犯罪収益移転防止法に基づく)であるのに対し、eKYCはオンライン上で本人確認を行います。
eKYCは、「electronic Know Your Customer」の頭文字をとった言葉で、オンライン上で本人確認を行う技術のことです。対面や郵送での本人確認を表す「KYC」に「electronic」を追加した造語です。「オンライン本人確認」「デジタル認証」と呼ばれることもあります。
2018年の犯収法改正でオンライン本人確認が可能に
2018年11月に「犯罪収益移転防止法施行規則」が改正されました。改正前は、一般的に対面や郵送などで、本人確認を実施していました。しかし、法改正により、郵送による本人確認はより厳重になっています。
なりすまし防止が強化された一方で、本人確認のコスト負担を解消するため、オンライン上での本人確認に移行する企業が増えました。その結果、eKYCを導入する企業が増え、ニーズの高まりを見せています。
eKYCの導入が増加している理由
eKYCを導入する企業が増えています。ここでは、法改正、社会の潮流など4つの観点から増加傾向の理由を解説します。
犯収法改正(2020年・2022年)による本人確認の厳格化
2020年4月には犯罪収益移転防止法が改正されました。郵送による本人確認では、本人確認書類の種類が厳格化されるようになり、顔写真なしの身分証明書では受け取りができなくなっています。さらに、偽装書類による不正防止のため、2022年からはさらに厳格化が進んでいます。
現在、非対面での本人確認は、顔写真付きの身分証と、現住所が記載された本人確認書類を用意しなければなりません。eKYCであれば、本人確認書類は1つで済むことから、需要が高まっています。
非接触・非対面の潮流
デジタル化が進む現代社会において、対面から非対面に移行する世のなかの潮流もeKYCの導入を後押ししています。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、リモートワークのほか、オンライン決済やオンラインイベントが浸透しました。厚生労働省が感染症対策に「新しい生活様式の実践」を発表したことも大きいでしょう。
感染症対策や利便性の観点から、リモートワークやオンラインでの手続きなどが続くと予想されます。
eKYCの適用範囲拡大
2018年の防犯法改正後、楽天Pay、PayPayといったキャッシュレス決済サービスがeKYCを導入しました。2020年には、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」が改正され、新規契約やMNPの際に本人確認として、eKYCが利用できるようになりました。
また、不動産契約やクラウドファンディングの申し込みなど、幅広い範囲でeKYCの適用が拡大しており、今後も増えることが予測されます。非対面での手続きでも本人確認書類を送付する必要が無く、オンライン上で手続きが完了したことも、導入が増加した要因に挙げられます。
eKYC開発ベンダー・サービスの増加
eKYCでは、顔写真付きの本人確認書類に加えて、本人の容貌がわかる画像の送信を求める認証方法があります。これを満たすために必要となる、画像送信のための専用ソフトウェアを開発・提供するベンダーが増加したことも、eKYCが広がりを見せている要因の1つです。ツールの精度や操作性も向上しており、利便性も高まっています。
eKYCによる本人確認方法の種類
eKYCによる本人確認方法の種類は4つに分けられます。それぞれの方法について解説します。
【ホ方式】セルフィー(容貌画像)+本人確認書類画像
ホ方式とは自分の容貌と本人確認書類の写真を、専用のアプリにアップロードする方法です。本人が操作していることを証明するために、アップロードする写真は、その場で撮影することが求められます。仕組みとしては2つの写真を突き合わせて、本人で確認を行います。
本人確認書類について、容貌と合致しているかに合わせ、厚みやサイズなど、視認できる特徴が撮影できているかを確認できるものが主流です。
【ヘ方式】セルフィー(容貌画像)+本人確認書類のICチップ情報
ヘ方式は、アプリで撮影した顔と、運転免許証やマイナンバーカードに付属しているICチップの情報が合致しているかで本人確認します。ICチップの読み取りには、NFC機能を持つスマートフォンを利用します。ICチップは改ざんされにくく、セキュリティに長けており、信頼性を証明できます。
【ト方式】銀行API+本人確認書類画像/本人確認書類のICチップ情報
ト方式は、アプリで運転免許証、マイナンバーカードといった本人確認書類を撮影し、その後、顧客が口座を持っている銀行に問い合わせ、銀行APIと合致しているかを確認する方法です。ICチップ情報を送信することでも、本人確認が可能です。銀行APIによる本人確認は、手間がかかるため導入する企業は限られています。
【ワ方式】マイナンバーカードのICチップ情報(公的個人認証)
ワ方式は、マイナンバーカードのICチップ情報と、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)の公的個人認証サービス(JPKI)を組み合わることで、本人確認をする方法です。セキュリティレベルが高く、シンプルな操作で利用できる特徴があります。ユーザビリティが改善し、バックオフィスの負担が軽減することから、導入する企業は増加傾向です。
企業がeKYCを導入するメリット
eKYCを導入する企業が増えています。導入を後押しするメリットを5つの観点から解説します。
利便性向上による顧客満足度の向上
eKYCは、書類を郵送したり窓口を訪問したりする必要がなく、オンライン上で本人確認が完了します。手間が省けるため、顧客満足度が向上するでしょう。
スムーズな本人確認による顧客の離脱防止
従来の本人確認は、承認されるまでに数日から数週間の時間を要する場合もありました。また、手続きに時間や手間がかかると、申し込みや手続きを躊躇し、離脱する顧客が一定数存在しました。その点、eKYCはオンライン上でスピーディに本人確認が完了するため、顧客が興味を持ってから実際に利用開始するまでの時間が短縮できます。そのため、顧客の離脱を防ぎやすくなるでしょう。
本人確認手続きの工数削減・業務効率化
eKYCを導入すると、本人確認書類と顔写真をスマートフォンのカメラで撮影するのみで本人確認が完了します。郵送された書類を確認したり、管理したりする手間や工数が削減できるため、業務効率化につながるでしょう。
郵送コスト・人件費の削減
本人確認書類を郵送してもらう場合、郵送の手間や費用、人件費がかかります。また、本人確認業務は、書類の発送のほか、確認・整理・保管と多岐にわたります。さらに個人情報を扱うため、保管場所のセキュリティ面にも配慮しなければなりません。その点eKYCでは、本人確認書類を郵送したり、管理したりする手間が省けるのがメリットです。
なりすまし・不正利用の防止
eKYCでの本人確認は、なりすましを防止できます。これは、その場で写真を撮影したことを確認できる仕組みによるものです。本人確認書類の顔写真と、スマートフォンによる容貌の一致確認も不正防止に役立ちます。
eKYCを導入するデメリット
eKYCの導入を考える企業は、デメリットについても考えておく必要があります。ここでは、3つのデメリットを解説します。
対応するデバイスやアプリのインストールが必要
eKYCは、専用のアプリをインストールする必要があります。また、アプリは、推奨されている機種や動作環境があります。そのため、eKYCを利用するためにデバイスやアプリをインストールする環境を整える必要があります。
一部顧客の離脱を招く可能性がある
eKYCで個人情報を確認する場合、運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きの身分証明書を用意する必要があります。スマートフォンを持っていない、免許証やマイナンバーカードなどを用意できない顧客はeKYCでの本人確認ができません。また、デジタル機器に不慣れな高齢者層は手続きが負担になり、一部の顧客は離脱する可能性があります。
機器操作トラブル・エラーが発生する場合がある
スマートフォンで容貌を撮影する場合、照明やピント調整が必要です。状況によっては、予期せぬエラーやトラブルが発生することもあるでしょう。スムーズに個人情報の確認が完了しないと、一部の顧客は離脱する恐れもあります。
eKYCサービスを選ぶ際のチェックポイント
eKYCサービスを導入する際は、選ぶポイントを事前に把握しておきましょう。
「ブラウザ型」か「アプリ型」か
eKYCサービスは「ブラウザ型」と「アプリ型」に分けられます。顧客の年齢層や購買行動などを鑑みて、いずれかを選びましょう。
まずブラウザ型eKYCサービスは、eKYCのシステムと連携して本人確認ができます。新たにアプリをインストールする必要はありません。一方でアプリ型eKYCのシステムは、アプリをインストールする手間はかかりますが、アプリだけで本人確認が完了するため、顧客の手間が省けます。
対応している本人確認方式
eKYCサービスで個人情報を確認する方法は多岐にわたります。例として、以下が挙げられます。
- 顔写真と本人確認書類を組み合わせる方式
- ICチップを読み取る方式
また、利用できる本人確認書類もサービスによって異なります。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
セキュリティ面や顧客の利便性、ニーズなどを包括的に考えて、自社に合った本人確認方法を採用しているサービスを利用しましょう。
カスタマイズ性
eKYCにどのようなサービスを求めているかは、企業によって異なります。自社独自の審査フローや本人確認方法などに対応できるか、カスタマイズ性を確認しましょう。
UI・操作性
使いやすい、操作がわかりやすいといった視点も重要です。手順が複雑だったり、画面操作がわかりにくかったりすると、顧客の離脱や顧客満足度の低下などのリスクをもたらします。申請画面がわかりやすいか、必要に応じてガイドが表示されるか、スムーズに本人確認が完了する導線が設計されているかなどを確認しましょう。
セキュリティ対策・信頼性
eKYCサービスでは個人情報を扱います。そのため、厳格なセキュリティ体制は不可欠です。データの暗号化や通信の保護、監査ログの記録や不正利用の検知機能などの機能が備わっているかを確認しましょう。
セキュリティ対策が不十分なeKYCサービスは、個人情報書類やデータが漏洩したり、偽造されたりするリスクが高まります。トラブルが発生するばかりか、企業としての信頼を失い、業務に影響を与えかねません。eKYCサービスはセキュリティ対策と信頼性を必ず確認しましょう。
まとめ
eKYCが増加している背景には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されたことや、世の中が対面から非対面に移行していることなどが挙げられます。利便性の向上や業務効率化などのメリットがあることから、多くの企業がeKYCを導入しています。ただしeKYCを導入する際は、とくに金融業界では、個人情報の取り扱いに注意しなければなりません。
株式会社カンテックでは、高セキュリティのBPOサービスを提供しています。金融業界を取引先に持ち、お客様と長いお付き合いをいただいています。国内に事業所があり、在宅を使用していないことも特徴です。詳しくは以下のリンクよりお問い合わせください。