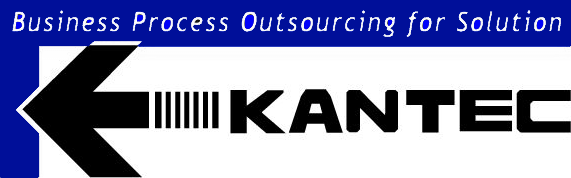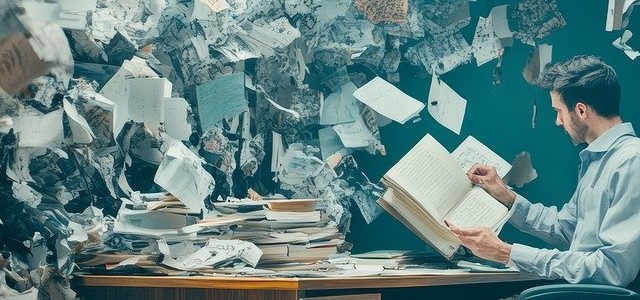こんにちは。BPOサービスを提供するカンテックのライターチームです。書類を電子化することには、複数のメリットがあります。例えば、テレワークに対応できる、コストを削減できるなどです。
この記事では、書類の電子化について進めるメリットやデメリット、進め方、注意点などを解説します。書類の電子化を検討している企業担当者は、ぜひご参考ください。
- そもそも書類の電子化とは?
- 紙の書類を電子データに変換すること
- 電子化に注目が集まる背景
- 電子化文書と電子文書の違い
- 書類を電子化するメリット
- 書類を電子化するデメリット
- システム導入にコストがかかる
- 資料の閲覧性が低下する
- オペレーションが変わる
- 機器の障害が起こるリスクがある
- 書類を電子化する方法
- スキャン業者へ依頼する
- コピー機・複合機を用いる
- スキャナーをレンタルする
- 書類撮影アプリを使用する
- 書類の電子化へ向けた5ステップ
- 書類を電子化する際の注意点
- セキュリティ対策をする
- 導入ソフトは慎重に検討する
- 関連する法律を確認する
- 書類の電子化に関連する法律
- まとめ
そもそも書類の電子化とは?
書類の電子化とは、紙で管理していた書類を電子データ化することです。ここでは、電子化の詳細や注目される背景について解説します。
紙の書類を電子データに変換すること
書類の電子化は、紙の書類をデジタル形式に変換する作業です。具体的には、紙の書類をPDFやJPGなどの電子ファイルに変換し、コンピューターやクラウドに保存することで、簡単にアクセスできるようにします。
電子化に注目が集まる背景
近年、電子化が推進される背景には、過去における「電子帳簿保存法」や「e-文書法」などの法整備があります。また、働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うテレワークの急速な普及も大きな要因です。
電子化文書と電子文書の違い
電子化文書と電子文書はよく混同されますが、それぞれ定義が異なります。電子文書は、コンピューターソフトウェアで直接作成された文書を指します。一方で電子化文書とは、紙の文書をスキャナーでデジタル化したものを指す言葉です。
書類を電子化するメリット
書類を電子化することには、さまざまなメリットがあります。セキュリティ対策になる、検索性が向上するなどです。それぞれについて解説します。
テレワークへ対応できる
書類を電子化すると、社外からでもデータに簡単にアクセスできるようになります。例えば、VPNを使って社内のファイルサーバーにアクセスしたり、クラウドストレージを利用したりする方法があります。
コストを削減できる
書類を電子化すると、印刷コストを削減できます。一般的に、A4サイズの資料を白黒でプリントする場合、1枚あたり約3~5円のコストがかかりますが、電子化されたファイルを共有すればそのコストは不要となります。
セキュリティ対策になる
紙の書類は、紛失や持ち出しのほか、劣化や消失などのリスクもあります。しかし、電子化することで、データのバックアップができるようになります。さらに、アクセス権限の管理やログの記録によって、セキュリティを強化することも可能です。
検索性が向上する
書類を電子化することで、検索性が向上します。具体的には、ファイルサーバーやクラウドストレージを利用して、簡単に目的の書類を探せるようになります。
業務効率化が図れる
書類の電子化は、業務の効率化に役立ちます。経費精算や受発注などのプロセスを電子化することで、紙の書類を手作業で入力する手間やエラーを減らせます。
書類を電子化するデメリット
書類を電子化することには、デメリットもあります。システム導入にコストがかかる、オペレーションを変更する必要があるなどです。それぞれについて解説します。
システム導入にコストがかかる
書類を電子化する際には、機器を導入するコストが発生します。そのため、コスト削減や業務効率化などの費用対効果を計算することが重要です。
資料の閲覧性が低下する
書類を電子化すると、紙の書類よりも読みにくくなることがあります。特にモバイル端末などのディスプレイサイズが制限されている場合、文字が小さくなり読みづらくなるでしょう。
オペレーションが変わる
書類を電子化することで、オペレーションが変わることがあります。一部の従業員は、変化に抵抗を示すかもしれません。そのため、電子化を進める際は目的や意義を明確にし、従業員からの理解を得ることが大切です。
機器の障害が起こるリスクがある
書類を電子化すると、ファイルサーバーやHDD(ハードディスクドライブ)などにデータが保存されます。しかし、これらの機器に障害が生じる可能性はゼロではなく、大手クラウドストレージも同様のリスクがあります。障害が起きると業務停止する恐れがあるため、リスク対策を十分に行いましょう。
書類を電子化する方法
書類を電子化する方法は複数あります。それぞれの特徴を理解し、自社に適した方法を選びましょう。
スキャン業者へ依頼する
大量の書類を処理する場合は、多くのリソースが必要なため、外部のスキャン業者に依頼することをおすすめします。スキャン業者へ依頼すれば、機材やツールを用意する必要がありません。
コピー機・複合機を用いる
手軽な方法は、オフィスにある複合機を利用して書類を電子化することです。社内でよく使われているため、従業員も操作に慣れており、スムーズに進められます。また、万が一のトラブルが起きても、修理やサポートが確保されているので安心です。
スキャナーをレンタルする
書籍や大きな資料をスキャンする場合、スキャナーをレンタルする方法がおすすめです。スキャナーには大きく「自動スキャナー」と「手置きスキャナー」の2種類があります。
書類撮影アプリを使用する
書類撮影アプリを使用して書類を電子化することも可能です。ただし、大量の書類を処理する場合は、あまり効率的ではありません。少量の書類や急ぎのときに手軽に使える方法です。
書類の電子化へ向けた5ステップ
大量の書類をデジタル化する際には、計画を立てて効率的に作業を進めることが鍵となります。以下のステップに沿って、電子化を進めましょう。
- 電子化する目的や目標を決めておく
- 対象となる書類を決める
- 電子データの保管や運用のルールを決める
- 電子化する方法を決める
- 電子化を進める
書類を電子化する際の注意点
書類を電子化する際は、いくつかの注意点があります。セキュリティ対策をする、導入ソフトを慎重に選ぶなどの注意点について解説します。
セキュリティ対策をする
電子化のスキャン作業を外部の業者に委託する際には、価格や納期だけでなく、セキュリティ対策も重要な要素です。業者に見積もりを依頼する際には、セキュリティ対策についても十分にヒアリングしましょう。
導入ソフトは慎重に検討する
目的に応じて、電子化した書類をどのように管理、共有、活用するかを決めた上で、ソフトウェアを導入するといいかもしれません。また、電子化だけでなく、RPAやAI-OCRなども導入することで、業務フローを大幅に改善できる可能性があります。
関連する法律を確認する
書類を電子化する際には、関連する法律を確認することも大切です。書類の種類に応じて異なる法律が適用されることがあります。具体的な書類の電子化が決まった場合は、個別に法律を確認するようにしましょう。
書類の電子化に関連する法律
ビジネスで使用する書類のなかには、保管について法律で定められているものがあります。ここでは、関連する法律について解説します。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は、所得税法や法人税法などに特別の規定を設け、国税関連の帳簿書類の保存方法について定めた法律です。紙での保存だけでなく、電子化文書や電子文書としての保存を認め、その要件や方法を規定しています。
電子署名法
電子署名法は、2001年に制定された法律です。特定の条件を満たす電子署名が施された電子文書は、本人の意思に基づいて作成されたと推定されます。これにより、本人による物理的な署名や押印と同等の法的証拠力が認められるようになりました。
IT書面一括法
IT書面一括法は、書面の交付や提出に関する情報通信技術の利用の促進に関する法律です。特定の条件を満たす場合に、電子メールやFAXなどの電子的手段で書類の交付や提出が認められます。
e-文書法
e-文書法とは、民間企業が行う書類などの電子化保存を認めるために定められた、次の2つの法律の総称です。
- e-文書通則法(民間企業等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)
- e-文書整備法(民間企業等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
e-文書法の施行前は、多くの書類が紙での保存に限られており、業務効率の妨げとなっていました。電子保存が技術的に可能になったことを受けて、e-文書法が整備されました。
デジタル改革関連法
デジタル改革に関する法律は、デジタル技術の普及と活用を促進し、国民の生活と経済活動を支えるためのデジタルインフラ整備を目的とする法律です。2021年に制定され、6つの法律で構成されています。
まとめ
書類を電子化することで、リモートワークに対応できるだけでなく、コスト削減や業務効率化にもつながります。しかし、大量の書類を電子化するには、多くの時間がかかります。
人員を割くのが難しい場合は、株式会社カンテックへご相談ください。弊社は国内に事業所を構え、在宅作業を使用していないため、高いセキュリティ体制を整えています。一連の作業を包括的にお任せいただけます。気になる方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。