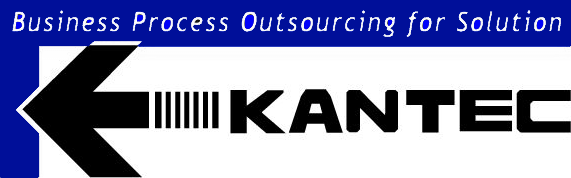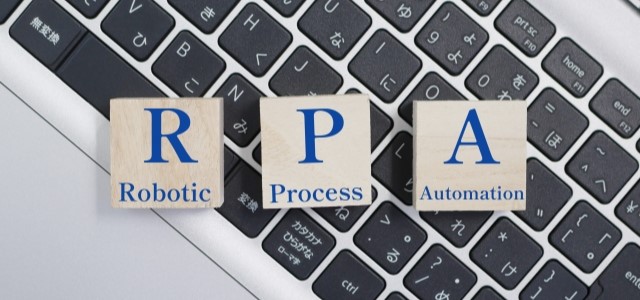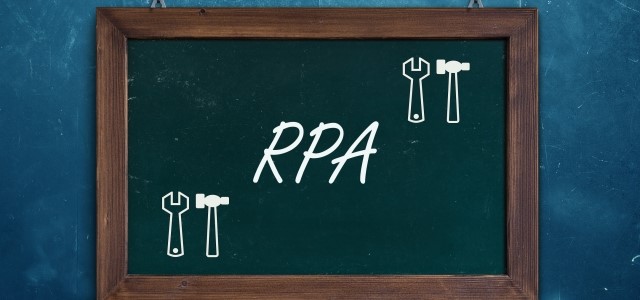こんにちは。BPOサービスを提供するカンテックのライターチームです。RPAとマクロは、どちらもパソコン上で業務を自動化するものです。処理の手順を自動化し、事務をはじめとした業務の効率化につなげます。それぞれ得意分野が異なるため、事前に業務の選定をすることが必要です。この記事では、RPAとマクロの違いや共通点などを解説します。導入する際のポイントも解説するため、ぜひ参考にしてください。
RPAとは
「RPA(Robotic Process Automation)」とは、パソコン上の業務を自動化するロボットです。主にバックオフィスの業務を自動化し、業務効率化を実現します。別名「仮想知的労働者(デジタルレイバー)」とも呼ばれており、定型業務や単純作業などを効率化するのに適しています。
Excelのマクロとは
Excelのマクロとは、作業を自動化する機能の1つです。ワンクリックのみで、登録した一連の作業手順を処理できます。マクロは数値の管理や加工などと相性がよく、WordやPowerPoint、Accessなどにも備わっています。
マクロとVBAの違い
「VBA(Visual Basic for Applications)」は、プログラミング言語の1つです。一方でマクロは、処理を実行するための機能です。一つひとつの自動化の処理がVBAで、ひとまとめにしたものをマクロと考えるとよいでしょう。マクロの処理する内容を実行するために、VBAを使用して処理します。
RPAとマクロの違い
RPAとマクロは、作業の範囲や処理の速度などが異なります。ここでは、それぞれの違いを解説します。
自動化できる作業の範囲
マクロは、Microsoft社のアプリ上で動作します。RPAの動作は、ExcelやWordなどMicrosoft社のアプリだけではありません。複数のアプリやシステムなどを横断して、作業の自動化ができます。たとえば、Webサイトからデータをダウンロードして、Excelでデータ処理を行い、チャットツールに貼り付けることが可能です。
プログラミングの必要性
マクロではVBAのプログラミング言語を使用し、コードを書いて動作を指定します。一方でRPAでは、プログラミング言語の知識が不要です。テンプレートやシナリオ機能などを使用して、自動化する作業を設定できます。ただし、プログラミングの知識があると、複雑な作業やメンテナンスをする際に便利です。
データの処理量・処理速度
マクロはパソコン上で動作するため、処理速度や処理量は端末のスペックに左右されます。デスクトップ型のRPAも同様に、パソコンの性能に依存します。一方で、クラウドやサーバー上で稼働するRPAであれば、端末の性能に関係なく、高速かつ大量のデータ処理が可能です。
連携できる範囲
マクロが連携できるのは、ExcelをはじめとしたMicrosoft社の製品です。一方、RPAを使用する場合は、他社製品でも連携できます。たとえば、データベース連携やAPI連携、ファイル連携の機能などの利用が可能です。既存システムと連携する際も、作業の自動化を実現できます。
導入にかかるコスト
マクロはExcelに標準搭載されているため、Excelさえあれば基本的に追加のコストは発生しません。ただし、VBAの開発を外部に依頼する場合は、その分のコストがかかります。一方、RPAはツールやシステムの導入にあたってコストが必要で、対応できる業務範囲が広い分、月額数万円以上かかるケースもあります。
RPAとマクロの共通点
RPAとマクロには、得意な分野や更新の必要性などが共通しています。ここでは、それぞれの共通点を解説します。
ヒューマンエラーの削減が可能
RPAやマクロを活用すれば、作業の自動化によってヒューマンエラーを大幅に減らすことが可能です。人間のように集中力の低下や疲労の影響を受けないため、ミスが起こりにくくなります。特に、データ入力・分析・報告書作成といった時間のかかる定型業務に適しており、正確かつ効率的な処理が実現できます。
管理や更新の継続が必要
自動化した処理は、一度作って終わりではなく、継続的な管理や更新が必要です。アプリやシステムのバージョン変更によってエラーが発生することがあり、その際は処理の再設定やメンテナンスが求められます。また、担当者が変わる場合には、スムーズに引き継ぎができる体制づくりも重要です。
非定型業務の自動化が苦手
RPAやマクロは、定まった手順に従う作業は得意ですが、非定型業務の自動化には不向きです。たとえば、問い合わせ対応のように人間の判断や柔軟な対応が求められる業務には適していません。処理手順が一定でない場合、正しく動作させることが難しいためです。近年では、RPAとAIを組み合わせて非定型業務に対応する技術も開発されています。
RPAとマクロは組み合わせが可能
RPAとマクロは、併用することでそれぞれの強みを活かした柔軟な自動化が可能です。特に、業務でExcelを多用する場合は、RPAとマクロを組み合わせることで処理の幅が広がります。
たとえば、基幹システムの操作はRPAが担い、Excel内のデータ処理はマクロに任せるといった使い分けが有効です。個別の作業にとどまらず、業務全体を俯瞰してフローを設計することで、高い業務効率化を実現できます。
RPAとマクロどちらの導入がおすすめ?
RPAとマクロは、自動化したい業務内容に応じて使い分けることが大切です。ExcelなどのOfficeアプリ中心であれば、マクロの活用が適しています。
一方、Webブラウザや専用システムなどMicrosoft製品以外も含めて自動化したい場合は、RPAが有効です。RPAは大量データの処理に強く、金融・小売・製造業など、定型的な事務作業が多い業種に向いています。コストや運用体制も踏まえたうえで、自社に最適なツールや併用方法を検討しましょう。
RPAとマクロを導入する際のポイント
RPAとマクロの導入は、業務内容や予算などを考慮しましょう。ここでは、導入する際のポイントを解説します。
向いている業務で選ぶ
RPAとマクロは得意分野が異なるため、業務の適性を考慮しましょう。それぞれ適性に応じて、使い分けることが大事です。詳しくは以下の通りです。
RPAに向いている業務
RPAに向いている業務は、システムの連携が必要なものです。たとえば、財務会計や生産管理、販売管理などです。マクロでは処理のパワー不足になりやすいため、RPAによる大量のデータ処理を活用する必要があります。
また、スクレイピングという、Webサイトから大量の情報を収集することも適しています。売掛金の消込処理や取引先への支払い処理なども可能なため、銀行をはじめとした金融業界で活躍するでしう。
マクロに向いている業務
マクロに向いている業務は、Excelを使った売上管理表や請求書の作成などです。Excelシート間のデータ転記ができ、集計やグラフ作成といった自動化にも対応しています。Microsoft製品のみで完結する業務であれば、マクロを活用するとよいでしょう。
また、VBAを使いこなせる場合は、より柔軟なカスタマイズが可能です。ただし、VBAは処理速度が早い点がメリットですが、プログラミング言語の知識が必要な点に注意が必要です。
予算を考慮する
RPAとマクロは、予算をもとに導入を検討しましょう。システムの外注や担当者の常駐など、さまざまなコストがかかるためです。また、導入する際のコストだけでなく、運用のコストも考慮しなければなりません。セキュリティやサポートなどによっては、マクロよりRPAのコストが安くなる可能性があります。
サポート体制を確認する
マクロにはMicrosoftの公式サポートサイトが用意されていますが、専門的な開発やトラブル対応が必要な場合は、自力での対応が難しく、外部の専門業者に依頼するケースもあります。
一方、RPAは導入ツールに応じて、メール・チャット・技術者派遣など、ベンダーによる手厚いサポートが受けられるのが一般的です。導入後の運用やトラブル対応の安心感を重視するなら、サポート体制の充実度も重要な比較ポイントになります。
まとめ
RPAとマクロはいずれも業務の自動化を実現できる便利なツールですが、それぞれ得意分野が異なります。Excel中心の定型作業にはマクロ、複数のシステムを横断する処理や大量データの扱いにはRPAが適しています。
併用によって柔軟な業務改善も可能です。導入時は、自社の業務内容や予算、運用体制、サポート体制などを総合的に見極め、最適な手法を選びましょう。
株式会社カンテックは、豊富なノウハウと多岐にわたるサービス、徹底したサポートなど、一連の作業を包括的に提供します。国内の事業所は、在宅を使用しない高セキュリティが特徴で、金融業界の取引先と長いお付き合いをいただいています。ぜひ利用をご検討ください。