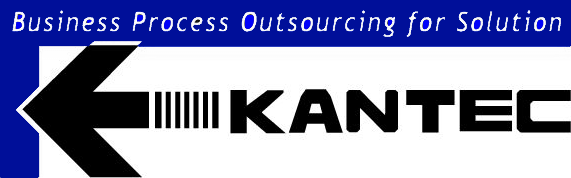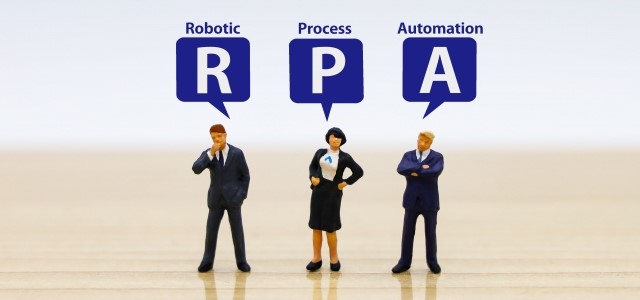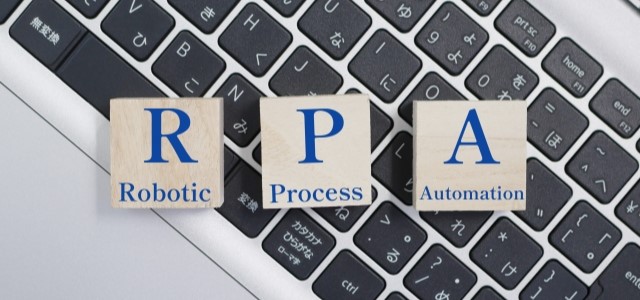こんにちは。BPOサービスを提供するカンテックのライターチームです。RPAは、定番化したルーティン業務を自動化できるツールです。本来の意味としては、人間の代わりにパソコン上で行う作業を実行する技術のことを指します。この記事では、RPAとは何か、3つのレベルや導入するメリットなどを解説します。RPAの導入を検討している方は、ぜひご参考ください。
- RPAとは?
- RPAの3つのレベル
- RPA導入における8つのメリット・効果
- RPAの効果測定方法
- 定量的効果の測定
- 定性的効果の測定
- RPAを導入する際の注意点
- 導入コストがかかる
- 情報漏えいのリスクがある
- 業務がストップする可能性がある
- 業務がブラックボックス化する場合がある
- まとめ
RPAとは?
RPAとは、定型的な業務を自動で処理するためのツールです。ソフトウェア上に存在する仮想的なロボットが、人間の代わりにパソコン上で行う業務を実行する技術を指します。データ入力や帳票の作成など、決まった手順で進められる業務の自動化が可能です。
また、RPAは「デジタルワーカー」とも呼ばれ、業務の流れをシナリオとして登録すれば、その通りに繰り返し作業を行ってくれます。時間や労力のかかる単純業務を人の手から切り離し、作業のスピードと正確性の向上が期待できます。
RPA導入が効果的な業務の特徴
業務効率を高める手段として、注目されているRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、特に特定の業務領域で大きな効果を発揮します。以下は、RPAの導入に適した代表的な業務の特徴です。
- コンピューター操作が中心となる業務
- 明確な手順が決まっている業務
- 作業の繰り返しが多い業務
RPAの3つのレベル
RPAには3つのレベルがあります。それぞれのレベルについて解説します。
RPA
一般的に「RPA」として認識されているのは、レベル1に分類される基本的なタイプです。おもにデータの取得や入力といった、繰り返しの多い定型業務を自動化するためのものになります。人がこれらの業務を行う場合、疲労や不注意によってミスが発生することがありますが、RPAは人的ミスを回避することが可能です。
EPA
RPAよりも一段階進んだ自動化を実現するのが、レベル2に分類されるEPA(Enhanced Process Automation)です。クラス1のRPAにAI技術を取り入れることで、定型業務にとどまらず、より複雑で柔軟性を求められる非定型業務にも対応できるようになります。例えば、AIによる画像認識機能を活用することで、請求書の画像から必要な情報を自動で抽出し、それをシステムに登録することが可能です。
CA
EPAよりも、さらに高度な自動化を実現するレベル3は「CA(コグニティブ・オートメーション)」と呼ばれます。さまざまな種類のデータを収集・解析し、その分析結果をもとに最適な判断を下す機能を備えたシステムです。ディープラーニング技術によって学習を重ね、自律的に進化していく点が大きな特徴です。
RPA導入における8つのメリット・効果
RPAを導入するメリットは複数あります。それぞれのメリット・効果について解説します。
業務のスピードアップ・効率化が図れる
複数のデータベースから情報を抽出・分析し、所定のフォーマットにまとめるといった手間のかかる業務も、RPAを使えばスピーディかつ正確に処理できます。対応時間の短縮により顧客満足度の向上が期待でき、さらに余ったリソースを他の重要業務に充てることが可能になります。
業務内容の可視化・改善ができる
RPAを導入することで、業務の流れを見直すきっかけになります。RPAを導入するには、まずどの業務を自動化するかを明確にする必要があるため、社内の業務を1つ1つ洗い出し、その手順や内容を詳細に整理する作業が不可欠です。実は非効率だった部分や、担当者によってばらつきが出やすい業務、不要な手順などが見えてきます。
人材不足の解消につながる
現在の日本では、少子高齢化の影響により労働力が減少傾向にあります。こうした状況のなかで、RPAの導入は、労働力の代替手段として有効です。人間と異なり、RPAは24時間365日で稼働可能です。従来、人手を要していた業務を担うことで、慢性的な人手不足の解消に大きく貢献します。
人件費の削減ができる
RPAを活用することで、これまで人手と時間を要していた定型業務を自動化でき、労働時間の短縮につながります。特に、手作業では工数がかかる単純作業をRPAが代行することで、業務効率が向上し、結果として人件費の削減が可能になります。
働き方改革・多様な働き方に対応できる
労働人口の減少や長時間労働の是正を背景に、働き方改革の重要性が高まっています。具体的には生産性の向上や、ワークライフバランスの実現、多様な働き方への対応などが求められています。
そこでRPAを導入すれば、定型業務が自動化され、従業員の負担軽減や労働時間の短縮が可能になります。その結果、テレワークや時短勤務など柔軟な働き方の実現にもつながるでしょう。
ミスの軽減・業務品質の均一化が実現する
RPAはあくまで設定された指示に従って動作するため、指示外の行動は行いません。その結果、手作業で起こりやすい「入力ミス」や「読み取りエラー」などのヒューマンエラーを減らせます。
さらに、RPAは業務の標準化にも有効です。例えば「担当者によって手順が異なる」「成果物の品質にばらつきがある」といった個人差による問題がある場合でも、RPAを活用すれば業務の品質を一定に保つことが期待できます。
従業員のモチベーション・従業員満足度の向上につながる
RPAによって繰り返し作業や単純作業が自動化されることで、従業員は自らのスキルを活かせる創造的な業務や意思決定に関わる業務に集中できます。やりがいや達成感を得やすくなり、仕事への意欲や満足度の向上につながります。
現場レベルでDX推進ができる
RPAツールの中には、プログラミングの専門知識がなくても直感的にロボットの設計や修正ができるものも存在します。こうしたツールを活用すれば、情報システム部門に依存せずに現場の視点からDXを推進できます。現場のニーズに基づいて作られたロボットは実務に適していることが多く、業務プロセスやルールの変化にも柔軟に対応できるでしょう。
RPAの効果測定方法
RPAの効果を測定するためには、定量と定性、両側面から測定しなければなりません。それぞれの測定方法について解説します。
定量的効果の測定
定量的効果とは、数値で示すことが可能な成果を指します。RPAによって得られる効果のうち、特にわかりやすいのが人件費の削減です。例えば、1年間でどれだけの人件費を節約できたかを把握するには、以下の計算式が役立ちます。
1年間の人件費削減額=担当者が1件の作業にかかる時間×担当者の時給×RPAが1年間に処理した作業件数
さらに、削減した人件費の金額とRPAの導入費用を比較することで、費用対効果の評価が可能です。
定性的効果の測定
定性的効果とは、数値化が難しい影響のことであり、定量的効果とは異なります。具体的には「従業員のやる気が向上した」「働く環境が改善された」といったものが該当します。これらの効果が波及して業務の円滑な遂行につながり、結果的に売上の増加をもたらすこともあります。数値での把握が難しいために、RPAの効果はつい定量的な面だけで評価されがちです。
RPAの導入効果を正確に捉えるためには、定性的効果も含めて総合的に判断することが欠かせません。導入前にアンケートなどを実施し、定性的な目標を明確にしておくことで、導入後との比較がしやすくなります。
RPAを導入する際の注意点
RPAを導入する際の注意点として、コストや情報漏えいのリスク、業務がストップする可能性などを解説します。
導入コストがかかる
RPAを導入する際には、ツールの選択や指示書の作成、業務内容の整理などにコストがかかります。導入後も、従業員向けの研修に加え、ロボットの構築や動作確認などの作業が必要です。これらを日常業務と同時に進めるのは困難なため、専門業者に委託する場合もあります。
また、RPAツール自体の利用料金が年間で数百万円程度かかる場合が多いため、自動化できる業務が限られていると、投資に見合った成果を得るのは難しいでしょう。
情報漏えいのリスクがある
取得したデータを社内システムに自動登録させるために、RPAに社内システムのIDやパスワードを組み込むケースがあります。しかし、プログラムのバグや操作ミスなどにより、不正アクセスのリスクが生じることも否定できません。
万が一、RPAが悪意ある第三者に乗っ取られてIDやパスワード情報が漏れてしまうと、第三者が社内システムに不正にログインする恐れがあります。したがって、通信内容や機密情報を暗号化するなど、十分なセキュリティ対策を実施することが不可欠です。RPAツールの導入にあたっては、セキュリティ機能の有無を慎重に確認しましょう。
業務がストップする可能性がある
RPAはサーバーやパソコンに専用ソフトを導入して動作します。そのため、システムの不具合やバグ、サーバーの停止が発生すると、RPAも停止し、業務が止まる可能性があります。特に、多くの業務をRPAで自動化している場合、その影響は大きくなります。
突発的なトラブルを完全に避けることは難しいものの、定期的なメンテナンスやサーバー環境の強化を行い、リスクをできる限り軽減することが重要です。
業務がブラックボックス化する場合がある
RPAは、あらかじめ設定された手順に基づいて自動的に作業を行います。一度シナリオを組んでしまえば、日常的に業務の詳細や進め方を把握しておく必要はありません。しかし、担当者が引き継ぎを行わずに部署異動や退職をすると、RPAがどのような処理をしているのか理解できる人がいなくなり、業務の内容が見えなくなってしまいます。
こうなると、万が一、誤動作が起きても誰も問題に気づかない恐れがあります。RPAで実行している作業の内容をきちんとドキュメント化し、適切な引き継ぎを行いましょう。
まとめ
RPAは定型業務の自動化を実現し、業務の効率化やスピードアップ、業務内容の可視化・改善、人材不足の解消や人件費削減など、多くの効果が期待できます。また、働き方改革や従業員の満足度向上にも貢献します。
一方で、導入コストや情報漏えいリスク、業務停止やブラックボックス化の懸念もあるため、これらの注意点を踏まえた上で計画的に導入を進めることが重要です。RPAの効果を正しく測定し、継続的な改善を図りながら活用していきましょう。
RPAの導入で悩んでいる人は、カンテックをご検討ください。国内に事業所があるだけでなく、在宅を使用していないため、高セキュリティです。一連の作業を包括的にでき、取引先が金融業界のお客様で長くお付き合いいただいています。ぜひお気軽にお問い合わせください。