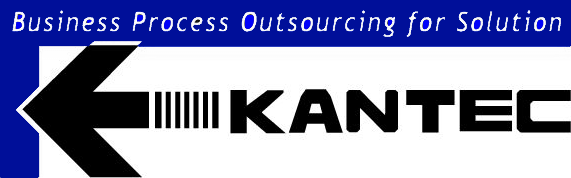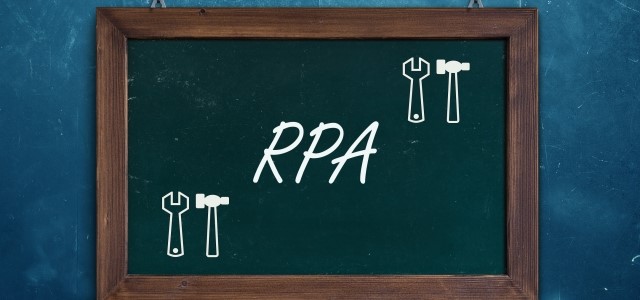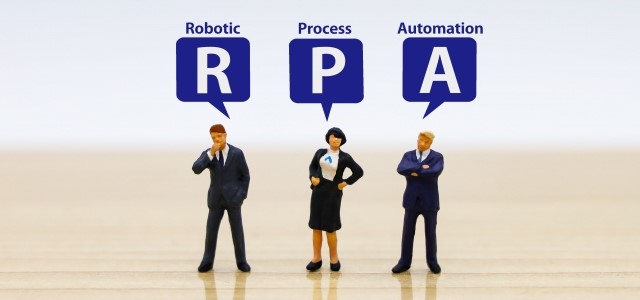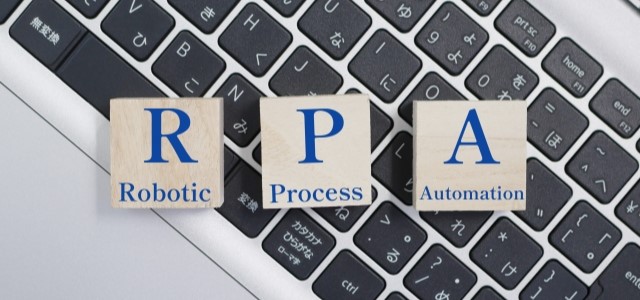こんにちは。BPOサービスを提供するカンテックのライターチームです。RPAの導入により、パソコンで行う定型業務の自動化を進める企業が増えています。この記事では、RPAの使い方のほか、RPAが注目されている理由やメリット、ツールの選び方などを解説します。RPAの導入を考える企業の担当者は、参考にしてください。
- RPAとは
- RPAの意味
- RPAとマクロの違い
- RPAとAIの違い
- RPAが注目されている理由
- RPAを使うメリット
- RPAの使い方
- RPAの使い方を誤るリスク
- 【部門別】RPAの活用事例
- 【業界別】RPAの活用事例
- RPAツールを選定する方法
- まとめ
RPAとは
RPAの基本的な意味や自動化できる業務内容について解説するとともに、マクロやAIとの違いについても紹介します。
RPAの意味
RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、ロボットによる業務自動化を指します。PC上で人間が行っている定型業務を、ソフトウェア型ロボットが代行する仕組みです。複雑なプログラミングを必要とせず、操作の記録や設定だけで導入できるため、データ集計や経費計算など、幅広い業種・業務で活用が進んでいます。
RPAとマクロの違い
RPAとExcelマクロは、いずれも業務を自動化する手段ですが、対応できる業務範囲に大きな違いがあります。
マクロはExcel内で完結する自動処理であり、複数のソフトや画面をまたぐ作業には対応できません。一方、RPAはExcel・ブラウザ・業務システムなど、複数のアプリケーションを横断して自動処理できるため、より広範な業務自動化が可能です。
また、マクロは基本的にプログラミングスキルが必要なのに対し、多くのRPAツールはノーコードまたはローコード設計で、非エンジニアでも扱いやすいように設計されています。
RPAとAIの違い
RPAとAIはどちらも業務効率化に貢献する技術ですが、得意分野と処理の仕組みが異なります。
RPAは、あらかじめ決められたルールに従って動作する「ルールベース型」の自動化で、定型的・繰り返し業務に強みがあります。たとえば、決まったフォーマットの書類作成や、毎日同じ手順で行う業務などが適しています。
対してAIは、データを学習し、パターンを認識・予測して処理する「判断型」の技術です。たとえば、画像認識や自然言語処理、異常検知など、人間の判断が必要な業務にも応用できます。
RPAが注目されている理由
昨今、RPAを導入する企業が増えています。ここでは、RPAが注目される理由を3つに分けて解説します。
生産年齢人口が減少しているため
RPAが注目される背景には、生産年齢人口が減少していることが挙げられます。内閣府「令和4年版高齢社会白書」によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に達する見込みです。生産年齢人口は、今後も減り続けると予測されています。
※参考:高齢化の状況
※参考:総務省|令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少
働き方改革を実現させるため
厚生労働省が掲げる働き方改革の柱の1つが長時間労働の是正です。柔軟な働き方がしやすい環境整備などを目的として労働基準法が改正され、その内容には、時間外労働の上限規制のほか、年次有給休暇の取得なども含まれます。働き方改革の改正点として、以下が挙げられます。
- 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要がある
- 残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とする
※参考:働き方改革特設サイト
IT技術が進化しているため
IT技術が進化し、ITシステムやITツールを導入する機会が増えています。これらのシステムやツールを導入するには、IT技術の知識やスキルを持つ従業員が欠かせません。一方、一部のRPAでは設定にプログラミングが不要なため、ITスキルや知識のない従業員でも扱えるようになっています。
そのため、IT導入の敷居が低く、アジア各国でも国の支援により、RPAの導入が進んでいます。日本でも、IT教育の強化やインフラ投資により、効率的にRPAを導入する企業が増えています。
RPAを使うメリット
RPAを導入することで、従業員や企業にとってどのようなメリットがあるのか、4つに分けて解説します。
コア業務に集中できる
RPAを導入することで、データ入力やファイル整理といった単純で繰り返しの多い業務を自動化させることが可能です。その結果、従業員は本来注力すべき戦略立案や業務改善、顧客対応などのコア業務に時間と労力を割けるようになります。付加価値の高い業務に集中できる体制が整うことで、生産性が向上し、企業全体の競争力強化にもつながります。
コスト削減につながる
RPAを活用すれば、これまで複数人で対応していた業務を自動化によって1台で代替できる場合があります。人手を減らすことで人件費の削減が可能となり、残業が多い業務であれば残業代の削減にもつながります。また、手作業によるミスの修正や確認作業も不要になるため、修正工数の削減による間接的なコストカットも期待できるでしょう。
人為的なミスを防止できる
RPAは設定された手順通りに正確に処理を行うため、人が対応する際に起こりがちなヒューマンエラーを防げます。特に、データ入力や経費計算などの単純かつ繰り返しの多い業務では、作業量の増加とともにケアレスミスが発生しやすくなります。その点、RPAを導入すれば、こうした人為的なミスを根本から排除し、業務の品質を安定して保つことが可能です。
従業員満足度が向上する
繰り返しの多い単純作業をRPAで自動化することで、従業員は業務の中でやりがいや達成感を得られる業務に集中できるようになります。自らのスキルや知見を活かせる業務に取り組める環境は、モチベーションの維持や向上につながり、結果として従業員満足度の向上が期待できます。
RPAの使い方
RPAの使い方は、業務の見直しから選定、開発書の作成といった3つのステップを踏みます。それぞれの工程について詳しく解説します。
1.業務の可視化、見直しをする
RPAを操作する前に、どのように使うのか、RPAの目的と合わせて事前に決めておきましょう。その上で、実際の業務を書き出し、業務に人員と時間をどれだけ費やしているかを洗い出します。実際の業務を可視化し、手順を見直すことで、業務の流れやボトルネックが明確になります。
2.自動化の対象とする業務を選定する
業務には、自動化に向いているものと不向きのものがあります。RPAは、人的判断を必要とする工程は自動化できません。部署ごとに業務を洗い出し、人手が足りていない、業務効率が悪い作業がどのくらいあるかを明確にした上で、自動化により効率化が期待できる業務を選定しましょう。
3.開発書を作成する
RPAで自動化する業務が決まったら、開発書を作成しましょう。RPAがどのように動作するか、誰が見てもわかる業務手順を記載した書類を作成することで、処理漏れや業務の重複を防げます。これにより、効率よく開発が進められるでしょう。
また開発書は、業務の流れだけでなく、関係する部署や担当者との役割分担を明確にする役割も担っています。こうした情報を整理することで、部門間の連携が円滑になり、開発工程での行き違いを防ぎやすくなります。
開発書が完成したら、その内容をもとに、実際にRPAが実行する業務のシナリオを設定していきましょう。
RPAの使い方を誤るリスク
RPAは非常に便利なツールですが、使い方を誤ると業務に深刻な影響を及ぼす可能性があります。代表的なリスクとして、誤った指示に基づく動作、業務の停止、そして管理不全によるトラブルなどが挙げられます。
もし異常や誤りに気付けないまま運用を続けると、誤送信や集計ミスなど、重大な業務トラブルにつながるおそれがあります。こうした事態を避けるには、設計時のミスに配慮するだけでなく、重要な処理に対して通知設定を行ったり、定期的な動作確認を実施したりすることが重要です。
また、RPAは他のシステムやアプリケーションに依存しているため、それらの仕様変更によって処理が止まるリスクもあります。例えば、ボタンの位置や画面構成が変わっただけでも、RPAは正常に動作できなくなることがあります。万一の停止に備えて、エラー時の対応手順や復旧マニュアルを事前に用意しておくと安心です。
【部門別】RPAの活用事例
各部門はRPAをどのように活用しているのでしょうか。3つの部門別に活用事例を紹介します。
経理業務
経理業務で自動化できる業務例は、以下のとおりです。
- データ入力
- 経費精算
- 請求書の送付業務
- 入金データのインポート
- 支払消込
総務・人事業務
総務・人事業務で自動化できる業務例は、以下のとおりです。
- 入社手続き
- 勤怠管理
- 採用関連の書類処理
- 新入社員のアカウント発行作業
- 給与計算
- 社会保険の書類変更
営業事務
営業事務で自動化できる業務例は、以下のとおりです。
- 顧客情報の登録
- 営業日報作成
- 見積書作成
- 見込み客のリストづくり
- 見積・請求書の作成
- 在庫確認のメール送信
【業界別】RPAの活用事例
続いて、業界別にRPAの活用事例を紹介します。
製造業界
製造業界で自動化できる業務例は、以下のとおりです。
- EDIシステムから自社システムへの取り込み
- 在庫数の管理
- 発注データのダウンロード
- 図面データのフォルダへの保存
- 請求書や納品書の整理・保存
- 生産ロット完了後のデータ登録
金融業界
金融業界で自動化できる業務例は、以下のとおりです。
- 振替処理
- 口座開設処理
- 顧客データの収集作業
RPAツールを選定する方法
RPAをどのように選定すべきか、3つの観点から解説します。
RPAツールの種類から選ぶ
RPAはサーバー型、デスクトップ型、クラウド型の3つに分けられます。導入の目的や用途に合わせて、適切なタイプを選びましょう。
| サーバー型 | 自社が保有するサーバーにインストールして利用する |
| デスクトップ型 | パソコンにインストールして利用する |
| クラウド型 | インターネットを通じてシステムを利用する |
サポート体制から選ぶ
RPAを導入し運用する過程では、操作方法や仕様について疑問や不安が必ず生じます。そのため、導入前から利用中まで、手厚いサポートが受けられるRPAツールを選ぶことが大切です。
また、ベンダーによっては設定の代行サービスや、従業員向けの研修・トレーニングを提供している場合もあります。自社のITリテラシーや運用体制に合わせて、必要なサポート内容をしっかり見極めましょう。
操作のしやすさから選ぶ
RPAツールのなかには、エンジニアが行うような複雑な設定が必要な製品もあります。RPAは、自社の従業員が使いこなせなければ、意味がありません。ITに不慣れな担当者でも直感的に業務を自動化できるRPAツールを選びましょう。
まとめ
RPAは定型業務を自動化し、効率化やコスト削減を実現します。導入時には、業務の見直しや自動化対象の選定、開発書の作成がポイントとなります。一方で、誤った使い方はトラブルや業務停止の原因となるため、自社に合ったツール選びや充実したサポート体制が重要です。
業務コストの削減、効率化には、株式会社カンテックのBPOサービスをご利用ください。高いセキュリティ体制が整っており、在宅を使用せず国内の事業所で一連の作業を包括的に行っています。金融業界のお客様とも、長く取引が続いています。詳しくは、お問い合わせください。