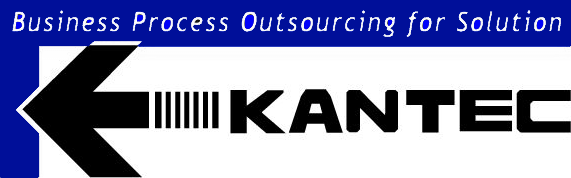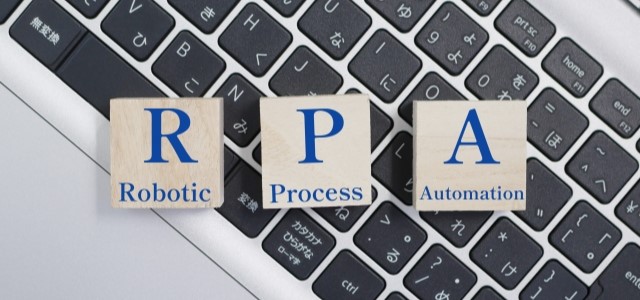こんにちは。BPOサービスを提供するカンテックのライターチームです。RPAを導入する際は、自動化する業務の選定基準や、運用の体制構築などが必要です。目的や目標を明確にして、長期的な視点をもって運用すると、効率的な活用ができます。
この記事では、RPAが「意味ない」といわれる理由や課題・成功のポイントなどを解説します。運用する際の注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。
RPAとは
RPA(Robotics Process Automation)とは、自動化のソフトウェアのことです。パソコンを使用する定型業務を自動化し、業務効率化につなげられます。たとえば、データ入力や集計、勤怠管理などの自動処理が可能です。RPAを導入すると、作業ミスや遅延も防げるため、既存の業務を効率化できます。
RPAが意味ないといわれる理由
RPAを活用する際は、業務やツールなどを考慮する必要があります。ここでは、RPAが意味ないといわれる理由を解説します。
自動化に不向きな業務を選んでいる
RPAは、すべての業務を自動化できるツールではありません。対象の業務によっては、自動化に不向きな可能性があります。たとえば、意思決定が必要だったり、業務内容が複雑だったりする場合、自動化の実現は期待できません。RPAを活用する場合は、同じ動作を繰り返す業務を対象とする必要があります。
ツールの操作が難しい
自動化の効果を最大限活用するためには、ツールの操作に慣れることが必要です。ツールの操作が難しく感じる場合、RPAの使用に慣れない可能性があります。またRPAを使用する際は、ITやプログラミングの知識や技術を求められる場合があります。自動化するプロセスを理解できていない場合、RPAの実装は困難です。
習得に時間がかかる
RPAの操作を習得して、自動化を実現するまでには時間がかかります。導入後にツールの使用に慣れない場合、現場に定着させることは難しいでしょう。多機能なツールであっても、習得に時間がかかって運用を辞めるケースもあります。そのため、RPAを導入する際は継続的に情報を収集し、学習を続ける必要があります。
運用体制を構築していない
RPAは、運用体制の構築が必要です。管理者や担当者がいない場合、定期的な保守やエラーに対応できません。トラブル発生時の対応が遅れる場合、運用が停止する可能性もあります。ツールが定着しないことで、より業務を増やすリスクが高まる場合もあります。RPAを現場が使用できるように、従業員の理解を促すことが大事です。
コストに見合う効果を実感できない
RPAを活用する際、サービスを利用するコストがかかります。導入後に業務を自動化しても、費用対効果が見合わない場合、RPAは意味がないと感じるでしょう。事前に費用対効果を算出しない場合、ツールの導入が形骸化するリスクが高まります。RPAの導入前と導入後を比較し、コストに見合うかどうかを判断することが大事です。
RPAが必要とされる理由
RPAは、労働人口減少の対策や働き方改革の実現に役立ちます。ここでは、RPAが必要とされる理由を解説します。
労働人口が減少している
昨今、国内の労働人口が減少し続けています。少子高齢化によって、今後も15〜64歳における労働人口の減少は加速するでしょう。外国人労働者や女性の社会進出も進んでいますが、多くの企業にとって人手不足は共通しています。だからこそRPAは業種問わず導入されており、労働力不足を解消する手段として期待されています。
働き方改革の実現が求められている
働き方改革が普及し、テレワークをはじめとした多様な働き方が求められています。具体的には36協定の変更や有給取得の義務化なども進んでおり、経営効率の改善が必要です。その点、RPAを導入すると、業務効率や生産性を向上させ、コア業務や思考の必要な業務に専念できます。業務の負荷を軽減するだけでなく、ミスを減らして品質向上にもつなげられるため、RPAの導入が必要とされています。
RPA導入における課題
RPAの運用は、業務の選定や専門人材の不足などが影響します。ここでは、RPA導入における課題を解説します。
自動化する業務の選定基準がない
RPAを導入する際は、自動化する業務を選定することが大事です。自動化する業務量が少ない場合、ツールを導入するコストが高くなります。すべての定型業務を自動化すれば、業務効率が上がるわけではありません。自動化が不要な業務を選定する基準がない場合、RPAの活用は困難です。
専門の人材が不足している
RPAの開発や運用をする際は、ツールを使用するための専門知識が必要です。一部の人材のみが専門知識をもつ場合、導入が進まないケースがあります。また担当者の異動や退職によって、更新や再設定に対応できなくなる可能性もあります。そのため、RPAを長期的に運用する際は開発やメンテナンスがしやすいツールを選ぶことが大事です。
効果の測定をしていない
RPAは導入した後に、効果の測定が必要です。たとえば、作業時間の短縮やエラーの件数など、さまざまな効果を可視化しなければなりません。導入の効果を計測しない場合、改善点に気づかないまま使用を継続してしまいます。業務効率につながらずに、コストのみがかかる運用になるリスクもあるため注意が必要です。
RPA導入を成功させるポイント
RPAは明確な目的をもって導入しましょう。ここでは、導入を成功させるポイントを解説します。
目的・目標を明確にする
RPAを導入する際は、目的を明確にしましょう。運用する際の指針が決まることで、手段の目的化を避けられるため、課題の解決につなげられます。目的から逆算すると、KGI(最終目標)やKPI(中間目標)などが決まります。目標を具体的な数値で定めると、ミスの発生率や人件費の削減などの変化を比較することも可能です。
社内体制を構築する
RPAを定着させるために、社内体制を構築しましょう。専門家や専門知識をもつ人材などをチームに配属することで、スムーズな導入や運用ができます。従業員がツールを使いこなせるように、トレーニングできる環境も必要です。従来の業務フローを見直し、生産性向上や業務効率化につなげましょう。
現場のリテラシーに配慮する
RPAを活用するには、現場のリテラシーにあわせて運用する必要があります。ITのリテラシーが低い場合、現場のRPAの導入が進まない可能性が高まるためです。直感的な操作で使用できるツールを導入し、現場での活用をスムーズにすることが大事です。業者によるサポートも考慮し、最適なツールを選ぶとよいでしょう。
スモールスタートをする
RPAの運用は、スモールスタートがおすすめです。人材やコスト、時間などを節約でき、リスクを最小限に抑えた運用ができます。簡単な業務から自動化することで、仕組みや特性などの理解も深められます。小さい成功体験の積み重ねによって、周囲の理解を得やすくなるため、他部署への展開もしやすくなるでしょう。
外部ベンダーのサポートを受ける
RPAを活用する際は、外部ベンダーのサポートを活用しましょう。サポートが手厚い業者の場合、操作の習得だけでなく、現場で活用する方法のアドバイスも受けられます。万が一トラブルが起きた場合でも、スムーズな対処が可能です。外部ベンダーに依頼する際は、対応日時や問い合わせの方法などを確認しましょう。
RPAを運用する際の注意点
RPAの運用は、トラブルや情報漏洩などのリスクがあります。ここでは、運用する際の注意点を解説します。
誤作動やトラブルが起こる可能性がある
RPAはツールの誤作動やトラブルなど、不具合が生じる可能性があります。また他のアプリケーションと連携することで、処理に不具合が生じて誤作動を引き起こすこともあります。システム障害やエラーによって、業務停止につながるリスクを考慮することが必要です。被害を最小限に抑えるために、サポート体制の確認や、エラー時の対応などを決めておくとよいでしょう。
情報漏洩のリスクがある
RPAにも、外部から攻撃を受けるリスクがあります。サーバーやパソコンなどが悪意ある攻撃を受けると、情報漏洩につながります。セキュリティ対策として、アクセス権限や使用できる範囲などを設定することが必要です。状況に応じて、RPAの使用権限の範囲を変更することをおすすめします。
導入・運用のコストが発生する
RPAを使用するには、導入時と運用のコストがかかります。たとえば、クラウドやサーバーの構築、ITサポート、メンテナンスなどのコストです。またRPAは更新のたびにコストが発生するため、導入前に費用対効果が高いかどうかを判断しましょう。長期的な視点をもって、サービスを比較検討することが大事です。
まとめ
RPAを活用する上でのハードルとしては、業務の選定や運用体制の構築などが挙げられます。また、運用体制の整備やコストに見合う効果がないことから、RPAは意味がないといわれる場合があります。だからこそ、自社の業務に最適なツールを選び、RPAを効率よく活用するためには、外部ベンダーのサポートを受けるのがおすすめです。
株式会社カンテックは、豊富なノウハウと多岐にわたるサービス、徹底したサポートなど、一連の作業を包括的に提供します。国内の事業所は、在宅を使用しない高セキュリティが特徴で、金融業界の取引先と長いお付き合いをいただいています。RPAの活用をご検討の際は、ぜひご相談ください。お問い合わせ・お見積り