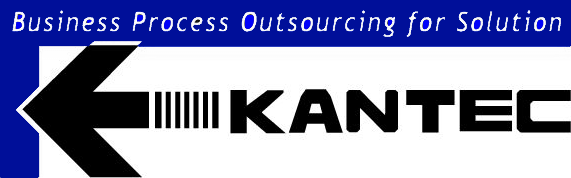こんにちは。BPOサービスを提供するカンテックのライターチームです。
業務の複雑化や属人化が進み、生産性の低下や手戻りの増加を課題としている現場の声は少なくありません。こうした状況を改善する有効な手段の1つに「業務設計」があります。業務設計を進める際には、業務全体を可視化し、目的やゴールを明確に定めることが重要です。
この記事では、業務設計の基本的な役割や具体的な進め方に加え、実務で役立つ代表的なフレームワークも紹介していきます。
業務設計とは
業務設計とは、組織の業務を整理し、流れや手順を最適化するための仕組みづくりを指します。ここでは、基本的な考え方や全体像について解説します。
業務設計が果たす役割
業務設計の役割は、業務全体を見渡し、重複や無駄を排除しながら効率的な流れを構築することにあります。個々の作業を分解して関連性を整理することで、担当者に依存しない仕組みを作ることができるのが特徴です。
人材不足や属人化による業務停滞のリスクを防ぎ、品質の均一化や生産性を向上させる上で欠かせない業務といえます。
運用設計との違い
運用設計は、システムやサービスを稼働させた後に安定して使い続けるための設計です。監視体制や障害時の対応、保守の流れを整理し、止まらない仕組みを整えることに重点を置いています。
一方で業務設計は、そもそもの業務のやり方や手順そのものを再構築し、効率化を目指す取り組みです。たとえるなら、業務設計が「道路そのものの設計」で、運用設計は「交通ルールや信号の整備」に近いイメージです。
業務設計を見直すときに意識すべきポイント
業務設計を見直す際には、単に手順を整理するだけでなく、改善の着眼点を明確にすることが重要です。ここでは、効率化やリスク低減につながる具体的なポイントを解説していきます。
属人化した非効率な業務プロセスを洗い出す
属人化は担当者の異動や退職で知識やノウハウが失われ、業務停滞を招く大きなリスクです。さらに作業効率が落ち、品質のばらつきも生じやすいため、業務設計を見直す際の重要な着眼点といえます。
まず「一定の人しかできない作業」をリスト化することから始めます。担当者へのヒアリングやフロー図の作成によって依存している業務を洗い出しましょう。
エラーや例外対応を見据えたリスク対策を組み込む
業務プロセスをどれほど綿密に設計しても、突発的なトラブルや例外処理を完全に排除することはできません。想定外に備えた仕組みがなければ、1つのエラーが全体に波及し、大きな損失につながる恐れがあります。
このリスクを抑えるには、まず過去のトラブル事例を洗い出し、発生しやすい業務を特定することが大切です。その上で代替ルートを設定し、進捗確認のチェックポイントを設けておきましょう。
ゼロから最適な業務フローを設計する
既存の手順に慣れていると「今のやり方が最善」と思い込みやすく、抜本的な改善が進みにくくなります。現状に縛られたままでは、非効率や無駄を抱えたままになるため、業務設計では基本的にゼロベースで理想の姿を考え直すことが重要です。
まずは現行フローを一度取り払い、最小限の手順で成果が得られる流れを設計します。その後、必要に応じて工程を追加し、ITツールや自動化の導入も検討しましょう。
前後の業務のつながりを意識して改善点を探す
業務を単体で改善しても、前後の流れを無視すれば全体の効率化にはつながりません。部門間の連携や情報の受け渡しに課題が残れば、結局は手戻りや遅延が発生してしまいます。
そのため業務設計では、前の工程からどのような情報や成果を受け取り、次の工程にどう引き渡すのかを具体的に整理していくことが重要です。これにより業務フローを可視化し、関係者にヒアリングを行うことでより効果的な改善点を見つけやすくなります。
目的を明確にして取り組む
目的が曖昧なまま業務設計を始めると、改善策の内容が散漫になり十分な成果を得られません。まずは「具体的に何を解決したいのか」「どこまで到達したいのか」を具体的に設定することが重要です。
実践方法としては、コスト削減率やミス削減件数など定量的な指標を決め、関係者と共有します。さらにQCD(品質・コスト・納期)のどれを優先するかを事前に合意すれば、判断基準がぶれず成果検証もしやすくなります。
業務設計の進め方
業務設計を効果的に進めるには、思いつきで改善策を導入するのではなく、段階を踏んで進めることが重要です。ここでは、ヒアリングから効果検証までの具体的な進め方をステップごとに解説します。
1. 各部門からのヒアリングと業務フローの可視化
業務設計の第一歩は、現状を正しく把握することです。誤った前提のまま進めると改善が的外れになりかねません。そのため、関係部門にヒアリングを行い、誰がどの手順で作業し、どのツールを使っているのかを明らかにします。
得られた情報は業務一覧やフロー図に整理し、現場担当者からマニュアルに載らない実態の情報も吸い上げましょう。こうして全体像を可視化することが改善の土台となります。
2. 課題抽出と改善方針の策定
次に必要なのは、業務の中で非効率やエラーが起きやすいものを洗い出すことです。課題を把握せずに取り組めば、効果の薄い改善で終わってしまいます。可視化した業務フローを基に、遅延やミスが多い作業を特定し、原因を深掘りしましょう。
その上で影響度や緊急度を基準に優先順位をつけ「短期で解決すべき課題」と「中長期で対応する課題」に整理します。方向性が明確になれば改善が進めやすくなります。
3. 実行に向けた計画の具体化
改善方針を定めた後は、現場で実行できる形に落とし込む必要があります。計画が曖昧だと担当者が迷い、施策が形骸化してしまいます。スケジュールや担当者、必要なリソースを明確にし、進捗確認のタイミングや評価指標も設定しましょう。
たとえば「来月末までに承認フローを電子化」「週1回の進捗確認」のように、具体性を意識することが重要です。さらにリスクや代替案を盛り込むことで、実行段階の混乱を防げます。
4. 計画に沿った業務プロセスの実施
具体的に実行の計画を立てた後は、実際に新しい業務プロセスをスタートしていきます。変更内容にもよりますが、大幅に変わる場合は抵抗や混乱を招くため、段階的な導入も検討しましょう。
まずは小規模な部門や一部工程で試験的に運用し、既存のやり方と並行させながら問題点を確認します。大きな不具合がなければ対象範囲を広げていきます。その際には説明会やマニュアルを用意し、相談窓口も設けて、従業員の不安を減らすことが大切です。
5. 実施後の効果検証と改善
業務設計は一度導入して終わりではありません。効果を測定し、改善を繰り返すことで真価を発揮します。導入前に定めた指標を基準に成果を確認し、期待通りでなければ原因を分析して修正しましょう。
業務設計の見直しに活用できるフレームワーク5選
業務設計を進める際には「フレームワーク」を活用すると効果的です。フレームワークとは、物事を整理し、判断するための考え方や枠組みを指します。複雑な業務も一定の切り口で分析できるため、抜け漏れを防ぎ改善の質を高められます。ここでは、業務設計の見直しに役立つ代表的なフレームワークについて解説します。
ECRS
ECRSは「排除・結合・並べ替え・簡素化」の4視点から業務を見直すフレームワークです。たとえば不要な承認工程をなくす、似た入力作業を1つにまとめる、処理順序を入れ替えて効率化する、書類を様式化して記入を簡単にするといった改善に活用できます。
業務設計に組み込むことで、改善策を具体的に検討しやすくなり、優先順位も明確になります。
PDCAサイクル
PDCAサイクルは「計画・実行・評価・改善」を繰り返すことで継続的に業務を改善する枠組みです。たとえば会議の議事録作成において、まず効率化の計画を立て、ツールを試し、完成時間や誤字率を測定し、改善が必要なら別の方法を試すという流れを繰り返す手法です。
業務設計の実行後も、定期的に見直す仕組みとして機能します。
ロジックツリー
ロジックツリーは課題や原因をツリー状に分解して整理する分析手法です。たとえば「納期遅延が多い」という問題を「作業時間の超過」「承認待ちの長さ」「外部委託先の遅延」などに枝分かれさせ、さらに承認待ちを「承認者の不在」「確認件数の多さ」に細分化していきます。
原因を網羅的に把握できるため、業務設計の課題分析に効果的です。
KPT
KPTは Keep(続けること)・Problem(やめる/課題とすること)・Try(挑戦すること) の頭文字を取ったフレームワークです。たとえば「週報フォーマットは便利なので続ける」「紙の承認フローは遅いのでやめる」「チャットツールで承認依頼を試すことに挑戦する」といった形です。
短時間で実践でき、日常業務の改善や業務設計の見直しに役立ちます。
バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、製品企画から販売、アフターサービスまでの一連の流れを分解し、それぞれの工程でどの価値が生まれるかを確認する方法です。たとえば製造では品質管理、販売では顧客接点の多さといった強みを明らかにできます。
これにより、単なる効率化ではなく「どこに投資すべきか」「どこを改善すべきか」を違った視点で分析できます。
まとめ
業務設計は属人化や非効率を解消し、組織全体を最適化する上で欠かせません。仕組みを整えれば生産性や品質が向上し、競争力の維持にも直結します。一方で、自社だけでは専門知識や人材不足の壁に直面しがちです。
外部のBPOサービスを活用すれば、改善のスピードと精度を同時に高められます。カンテックはデータ入力や事務代行、DX支援まで幅広く対応し、精度と効率を両立した業務設計を実現いたします。プロセス改善を加速させたい場合は、ぜひご相談ください。